3 うっとり系
これまでお話ししたジャンルとは一変し、ポールがリスナーをうっとりさせるヴォーカルを聴かせます。
1 ヒア・ゼア・アンド・エヴリウェア
ポール自身、自己の作品の中でも最も誇りに思っている作品の一つです。ジョンも1980年のプレイボーイ誌のインタヴューで「ビートルズの作品の中で好きなものの一つ」と答えています。
そういえば、2017年4月の来日公演直前に、日本のファンからの質問に答えるコーナーがあり、そこで「ビートルズ時代に作った曲で一番好きな曲は何ですか?」との質問に「それも良く聞かれるんだけど、どの曲も自分の子どもみたいで決められないんだ。ただ、敢えて言えば『ヒア・ゼア〜』かな?」と答えていました。
ポールのヴォーカルももちろんですが、ジョンとジョージのハモりも素晴らしいので、コーラス系に分類してもおかしくありません。
ポールは、こう語っています。「私は、スタジオでヴォーカルをレコーディングする時、誰も知らないことだけど、マリアンヌ・フェイスフルのように歌おうと思っていた。どう歌って良いかわからない時は、例えば、ジェームス・ブラウンを思い浮かべてみる。彼だったらどう歌うかなって。あるいは、アレサ・フランクリンだったら、レイ・チャールズだったら。そんな風に考えてみるのも一つのヒントになるんだよ。」
「それで、私は、小さな声で殆どをファルセットで歌った。そう、私が彼女に抱いていたイメージでね。」
マリアンヌ・フェイスフルは、イギリス出身の女性シンガーで「エンジェル・ヴォイス」と呼ばれたように、デビューした当時は清楚で清らかな歌声でした。ミック・ジャガーの恋人だったこともあります。
ポールの歌声は、どこまでも甘く優しくアイム・ダウンやヘルター・スケルターで見せた強烈なシャウトをぶちかましていた人と同一人物とはとても思えません(^_^;)
ポールのヴォーカルは、テープの回転速度を落として収録し、再生の時にスピードアップしています。また、ダブルトラックされています。
2 アイ・ウィル
これは、ポールが本当にささやくように歌っています。2分にも満たない小品ながら、実に美しい曲ですね。 彼の才能ならもう少し長く作ることもできたはずですが、これはこれで良かったのかもしれません。

途中から息がピッタリと合ったハーモニーが登場しますが、それもそのはず、ポールが一人二役で高音と低音のパートをハモっています。
面白いのは、ポールがヴォーカル・ベースを入れていることです。「ドゥン、ドゥン、ドゥン」ってな感じで。ガラス細工のような繊細な曲なので、エレキベースでは強すぎると考えたのでしょうか。
3 ミッシェル
これまた美しいバラードです。ミッシェルというのはフランス人の女性で、彼女に対する愛を訴えているという歌詞になっているため、一部がフランス語になっています。
ところが、当時は歌詞が公表されていなかったため、ポールがフランス語で歌っているとは気付かず、聴こえたまま無理やり英語に直しました。「Someday monkey gone play piano song」とか「Sunday monkey won't play piano song」とか訳されていました。

あのね、「空耳アワー」じゃないんだからさ(^_^;)確かに、そう聴こえなくもないですが、少なくとも英語じゃないってことぐらい分かりそうなもんですよね?翻訳すると「ある日、猿がピアノ曲を演奏した。」とか「日曜日に猿はピアノを弾こうとしないだろう。」とか、ぶっ飛んだ内容になっています。何故、誰もおかしいと思わなかったんでしょうか?
ポールは、ビートルズのメンバーの中でただ一人、この曲で1966年度のグラミー賞最優秀楽曲賞を受賞しました。
4 エリナ・リグビー
この作品でもポールのヴォーカルの音程は、相変わらずパーフェクトでした。彼は、敢えて感情を抑え淡々と歌っていますが、それがむしろ主人公の痛ましい生涯を的確に表現しています。ポールのヴォーカルはもちろん、メロディー、ジョージ・マーティンの書いた弦楽四重奏×2の譜面、そして、歌詞が素晴らしい。
僅か3分でエリナ・リグビーという薄幸の女性とマッケンジー神父の姿や感情、どうしようもない絶望感を鮮明にリスナーの脳裏に浮かび上がらせることに成功しています。
冒頭でエリナ・リグビーが地面に落ちた米を拾っている間に、教会では結婚式が行われている。何と皮肉な取り合わせでしょうか?たったこれだけの状況を描写しただけで、彼女が極貧状態にあることが瞬時に理解できます。
ポールは、弦楽四重奏×2が短く高音で弦を叩いている間、in a church⤴、where a wed⤴、ding has been⤴と巧みにしゃくりを入れるパターンを3回繰り返すことで、楽曲全体に悲壮感を漂わせています。これを譜面通りに歌ってしまうと、フラットな感じになり、リスナーがあまり感情移入できなくなってしまうのです。ポールは、ヴィブラートが嫌いで掛けなかったのですが、その代わりこういったテクニックを随所で使っています。
ポールは、ストリングスとは別にリード・ヴォーカルだけをレコーディングしました。そして、それはADTにかけられ、ダブルトラックされました。ADTとは、同じテイクを2回繰り返さなければならなかったそれまでの技術に代わり、一度のテイクで2重のレコーディングができるシステムです。これはジョンの要求により、EMIのレコーディング・エンジニアであったケン・タウンゼントが開発したものです。

「All the lonely〜」のところがダブルトラッキングされているのは、言うまでもなく、この作品が伝えたいメッセージを強調するためです。
曲の冒頭の「Ah~、look at~」という箇所は、最初のテイクでは入っていなかったのですが、ポールが最初のテイクを終えた後に閃いて追加したのです。
この作品ではモノラル・ヴァージョンとステレオ・ヴァージョンでポールのヴォーカルが違っており、前者の方がやや音量が大きくなっています。不思議なのはステレオ・ヴァージョンの1番の歌詞の「Ele」という箇所だけがダブルトラックされていることです。ADTの不具合か操作ミスによるものかは分かりません。
ポールは、この曲でもビートルズのメンバーの中でただ一人、1966年度のグラミー賞現代グループ音楽部門の最優秀歌唱、演奏賞を受賞しました。
5 ブラックバード
ビートルズって本当にクリシェ(音階を半音ずつ上下させるテクニック)がお気に入りのテクニックのようで、この曲でも盛んに使っています。アコースティック・ギターを弾きながら入れています。
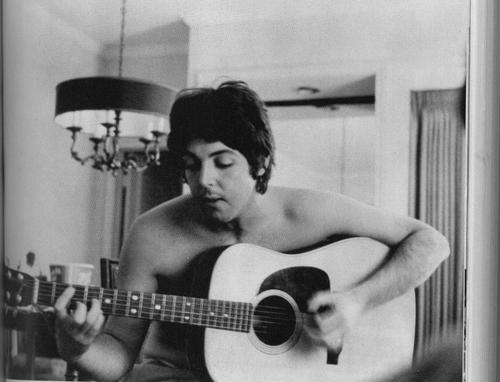
Aメロでの「Take these broken wings」のコードは、C→A7→D→B7→Emとなっており、ベースがC→C#→D→D→Eという半音上昇クリシェになっています。
「fly / All your lile / You were only waiting」 のコードは、
Em→EmM7→D→A7→C→Cm→G→A7→C→Gとなっており、ベースが前半ではE→D#→D→C#→C, 後半ではEb→D→C#→C-→Bという半音下降のクリシェになっています。
本当に複雑なことをやってますね(^_^;)頭が混乱しそうですが、ヴォーカルはあくまでも美しく、コード進行も卓抜しています。
6 シーズ・リーヴィング・ホーム
これまた美しい曲です。メロディーラインも素晴らしいし、荘厳なオーケストラ、そしてハープの格調高い調べがうっとりさせてくれる名曲です。これは、ハープ奏者のシーラ・ブロムバーグです。

ポールは、スローバラードで簡単に歌っているように聞こえるかもしれませんが、意外にヴォーカルが難しい曲です。
主人公の女性の哀しい心情を正確に理解しなければ、絶対にあの魂を震わせるような美しい歌声は出せません。また、ヴォーカルと4分の3拍子のオーケストラが密接に結合しているため、オーケストラにテンポを合わせるのが難しいんです。ですから、一つ一つの小節をテンポに気を付けながら丁寧に歌わなければなりません。
この曲では、モノミックスとステレオミックスが違っていて、後者ではテンポが少し遅くなっています。ビートルズが好んだテープの速度を変えるというテクニックをここでも使ったのですが、モノラルでは速度を速めてEのキーをFにしたのに対し、ステレオでは速度はレコーディングしたままの状態でした。どうやらうっかりテンポを変えることを忘れたみたいですね(^_^;)

ポールは、エンディングのタイトルコールのダブルトラックで音程を下げていき、甘くほろ苦い「bye bye」という歌詞で締めくくります。
ジョンが高音のパートをコーラスで重ねています。どうやれば上手くできるか、彼らは真剣に議論を重ねました。ポールは、完璧主義者の悪いクセが出てしまい、同じパートを何度もジョンにやり直させたため、彼が怒ってしまったのです。ポールのこういうところが後々解散につながるんですよね~( ノД`)
さて、次回は、「お茶目系」「野太い系」「コーラス系」に移ります。
(参照文献)THE BEATLES MUSIC HISTORY
(続く)

